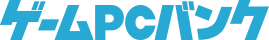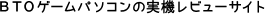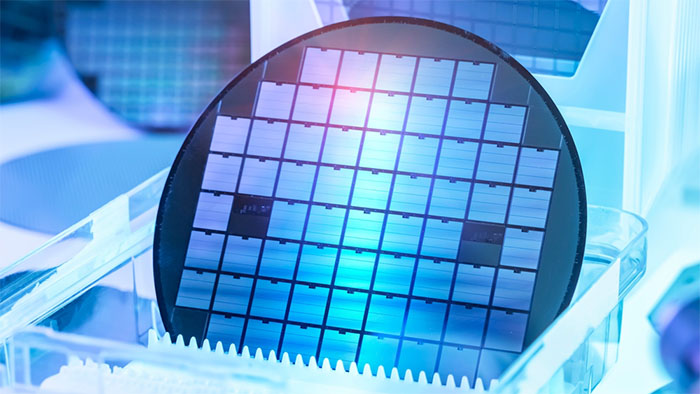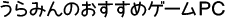当たりCPUは存在する?SPスコア(Silicon Prediction)と個体差論争の真実
投稿日:
※当ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
PC自作界隈でたびたび話題になる「当たりCPU」「シリコンガチャ」。同じ型番のCPUでも、個体ごとに動作特性が微妙に異なることは、多くのマニアが経験的に知っています。
その“個体差”を数値化したものが、SPスコア(Silicon Prediction)と呼ばれる指標です。この記事では、SPスコアの仕組みと活用法、そしてスコア至上主義に潜む落とし穴について解説します。
SPスコアとは何か?
SPスコア(Silicon Prediction)とは、CPUの製造時に発生する微妙な個体差を数値化した指標です。主にASUS製マザーボードでBIOSや専用ツール上に表示されます。
スコアは一般的に50~100程度の数値で表示され、数値が高いほど電圧効率が良く、オーバークロック耐性が高いとされます。
CPUは同じモデルでも、製造工程上どうしても性能にバラつきが生じます。その違いを判定するため、電圧と動作クロックの関係から「このCPUは高品質かどうか」を推測するのがSPスコアの役割です。
SPスコアが高いと何が違う?
一般的に、SPスコアが高いCPUほど、低電圧動作や高クロック動作が可能です。
オーバークロックやダウンクロック耐性が高いので、状況に応じた柔軟なCPUチューニングが可能になるわけですね。
例えば、同じRyzen 9 7950Xでも、SPスコア95の個体は1.25Vで5.4GHz動作できるのに対し、SPスコア70の個体では1.35V必要といった違いが出ることがあります。
結果として、発熱・消費電力・OC耐性に差が生まれるのです。
SPスコアは万能ではない
ただし、SPスコアはあくまでASUS独自の判定基準であり、全ての性能を保証するものではありません。スコアが高くても実際のOC耐性やベンチマークスコアが平均以下の個体も存在します。
また、SPスコアはシングルコア性能指標に寄っており、全コア負荷時の挙動と一致しないケースもあります。最近はマルチコア動作が普通ですから、あくまでも「性能指標のひとつ」という位置づけで考えたほうが良いかもしれません。
個体差論争とシリコンガチャ文化
このSPスコアを巡って、自作PC界隈では「当たり個体」「外れ個体」論争が繰り広げられています。
特に、中古市場でSPスコア付きCPUが高値で取引されることもあり、シリコンガチャ文化を加熱させています。
しかし、通常利用やゲーム用途では、SPスコアの違いを体感できる場面は少ないのも事実です。最近はオーバークロックも不要ですし、実使用でSPスコアが問題になるケースはまずありません。
OCベンチマーク競技者や、一部の超マニア層以外にとっては誤差の範囲ですね。あまり気にしなくて良いスコアだからこそ、公開したのでしょう。
実は個体差論争は大昔からあり、「安いCPUの当たりロット」は高額で取引されたりしていました。なので、今に始まった動きではないのです。単にSPスコアが可視化されたので、誰もが話題にしやすくなっただけのこと。
SPスコアは「参考程度」でOK
SPスコアは、CPU個体ごとの品質を数値化した、マニアには魅力的な指標です。しかしスコアに振り回されすぎると、本来のPC用途から逸脱しがちでもあります。
自作PCの楽しみ方は人それぞれですが、SPスコアはあくまで参考値として捉え、自分の用途に必要な性能を見極めて選ぶことが大切です。