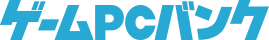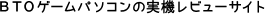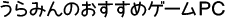中古グラボを買ったらまずやるべきこと3つ
投稿日:
※当ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
GPU価格の高騰や新品在庫の不安定さが続いています。そこで注目されているのが「中古グラボ」。
現在のグラボは中古でも十分な性能をもっていて、2~3世代前のグラボでも快適にプレイできることが多いです。
しかし、問題は「目利き」ができるかという点。中古品は見た目がきれいでも内部が劣化している可能性があり、トラブルに遭うケースも存在します。
こうしたトラブルを回避するためには、「買ってすぐのチェック」が欠かせません。今回は中古グラボを購入した際に、最初に行うべき3つのチェックについて解説します。
外観チェック – 見た目は嘘をつかない
グラボは、数十ワットから300ワットを超える電力を扱う精密部品です。
長い間、高負荷で使い続けると、基板やコンデンサ、ヒートシンクに「焼け」「膨張」「剥がれ」「ホコリの蓄積」などが出てきます。
こうした外観でわかる劣化を見抜くことがトラブルを回避する第一歩。
さらにヒートシンクの隙間に細かいホコリが詰まっていたり、ネジが一本だけ違う色をしていたりする場合は、修理歴や分解歴があるかもしれません。
また、コンデンサのトップが少しでも膨らんでいるようであれば、寿命が近いサインの可能性があります。
とくにマイニング用途で長時間フル稼働していたグラボは、ファンや電源回路が見た目以上に劣化していることが多いため、細部まで確認しましょう。
負荷テスト – 動作確認は必須プロセス
外観が正常に見えても、GPUの動作が安定しているとは限りません。そこで必ず行いたいのが、負荷テストです。
GPUに高負荷をかけて処理をこなし、温度や消費電力が異常な数値を示さないかを確認する作業ですね。
定番のテストツールとしては、3DMark(Time SpyやFire Strike)やUnigine Heaven/Valleyがあります。
これらのベンチマークソフトを使って20分以上連続でGPUを稼働させ、
- 急激な温度上昇がないか
- 画面にノイズ(アーティファクト)が出ないか
- 途中でドライバがクラッシュしないか
といった点を観察します。
また、GPU-Zなどのモニタリングツールを併用すると、クロックの変動やファン速度、VRAMの温度まで細かく確認できます。
マイニングに酷使されていた個体や、長期保管されていた個体は、この段階でエラーや熱暴走が発覚することが多いですね。
ファンの動作チェック – 異音・回転不足に注意
ファンが正常に回っているかも、忘れてはならないチェックポイントです。
グラボのファンは、長時間使用により軸のブレや潤滑不足が起こりやすく、劣化するとノイズや異音が発生するほか、回転数が上がらなくなることもあります。
一見して静かだからといって安心せず、ファンの動作ログを可視化できるソフト(たとえばMSI AfterburnerやHWiNFOなど)を使って、実際に回転数が上がっているかを確認しましょう。
また、ファン回転数を一時的に最大に設定し、「ジー」「カリカリ」といった異音がないか耳をすませて確認するのも有効です。
軸が歪んでいるファンは、最初は正常でも数時間のプレイで徐々にファンがブレはじめ、熱暴走を引き起こすことがあります。
ファンブレードの折れや歪み、油分の飛散、ヒートシンクとの干渉なども見逃さないようにしましょう。
失敗しない中古グラボ運用の第一歩
中古のグラボは、うまく選べばコストパフォーマンスに優れたです。私も何度か購入しましたが、明確な「はずれ」はほとんどありませんでした。
しかし、「買ってからのチェック作業」は必須です。見た目が綺麗であっても、ファンの微妙な異常や高負荷時の不安定動作は、使い始めて初めて気付くことが多く、何も確認せずに本番環境へ組み込むのは非常にリスキーです。
今回紹介した3つのチェックは、数時間以内に終えられるものでありトラブルを防ぐ重要な作業。購入後の初動で手を抜かず、きちんと向き合っておくことが、長く快適に使うコツと言えるでしょう。
ちなみに私の場合、少しでも怪しかったら使用せずにそのまま売却しています。