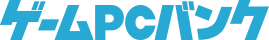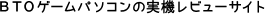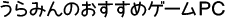「SSD乗り換え」のチェックポイント
投稿日:
※当ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
かつてHDD→SSDへの換装でPCを延命することが流行しましたが、今はSSDからSSDへの移行が主流です。
SATA SSDからNVMe SSDへの移行は、PCの体感速度を上げる最も簡単な方法のひとつになっています。
そこで今回は、今さら他人に聞きにくい「SSD乗り換え」のいろはについてお伝えしようと思います。
M.2 SSDには「SATA接続」と「PCIe接続(NVMe)」の2種類がある
M.2 SSDが登場して早5年以上が経過しましたが、いまだに「M.2 SSD=超高速」という勘違いをされている方がいます。
SSDなので高速なことに変わりはないのですが、M.2 SSDとは雑に言えば「形状」を表しているものであり、実際の中身は旧来のSATA接続の製品もあるのです。
SATA接続ならば転送速度の理論値は「約600MB/s」、PCIe接続(NVMe)ならば「約8,000MB/s」なので、約13倍も違います。
超高速と呼ばれるのはPCIe接続のM.2 SSDのほうですので、この点は十分に注意してください。
ちなみに両者は、接続部分の切り欠きで見分けることが可能です。SATA接続は、両端に切り欠きが各1個(計2個)あるのに対し、PCIe接続は片側に1個だけ切り欠きがあります。
SATAかPCIeかは、切り欠きの状態でですぐに見分けられるので、覚えておきましょう。
現在利用中のSSDよりも大きい容量を選ぶ
システムドライブのSSDを乗り換えるならば、現在使用しているSSDよりも大きな容量を選ぶようにしましょう。これは単純に気分の問題ではなく、クローンやデータ移行が楽になるからです。
クローンツールを使用してシステムドライブを丸ごと移行する場合、移行先のSSDで使われない領域は「未割当て」として扱われます。
この未割当て領域はあとから新しいパーティションとして使用してもよいですし、既存のパーティションと合体させて容量を拡張してもよいのです。どちらにしても余った領域の扱いはゆっくり決めれば良いだけの話。
一方、大容量→小容量でのクローンは、クローンする領域を事前に決めたり、データの削除を行ったりと、面倒な手続きが多くなります。
システムドライブとして適切な容量は大体250~1TBの間です。私はシステムドライブ(Cドライブ)とDドライブを物理的に分け、なおかつ最低限のデータしか置かないので、500GBでも十分です。
しかし、人によっては1台のSSDでC・Dドライブを賄うこともあるでしょうから、そういった場合は1TB以上が適切ですね。
今はPCIe接続のM.2 SSDも1TBクラスが非常に安くなり、1万円台前半で購入することが可能です。例えば、WESTERN DIGITALの「WD_Black SN770 NVMe WDS100T3X0E」などですね。
PCI-Express Gen4対応、かつ容量1TBでありながら価格は12500円程度。人気商品ですが、入手性もよくておすすめのSSDです。
SSDの寿命を延ばす「オーバープロビジョニング設定」
SSDには容量の一部をキャッシュのように使うことで、ランダムアクセス性能や寿命を延ばす機能が搭載されています。
この機能は「オーバープロビジョニング」と呼ばれていて、一部のSSDで自由に設定することが可能です。
オーバープロビジョニングで使用する領域を大きくすればするほどランダムアクセス性能や寿命が延びやすく、小さくすると使用可能容量が大きくなります。
一般的には7%程度がオーバープロビジョニング用として確保されているでしょう。SSDの専用ツールでカスタマイズできるので、気になる方は調べてみてください。
また、オーバープロビジョニングを変更できないSSDもたくさんありますので、事前にチェックにしておきましょう。