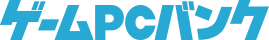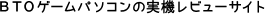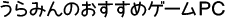MSIの「メモリトレーニング」機能とは?安定動作のための自動調整プロセスを解説
投稿日:
※当ページはアフィリエイトプログラムによる収益を得ています。
自作PCユーザーにとって、メモリの安定性はシステム全体の信頼性を左右する重要な要素です。
MSIのマザーボードには「メモリトレーニング」という機能が搭載されており、起動時にメモリの状態を最適化する役割を果たしています。
比較的新しい機能ですので、「メモリトレーニング」とは何か、どういった仕組みで動作するのかといったところから基礎知識をまとめてみました。
メモリトレーニングとは何か
「メモリトレーニング」とは、PCの起動時にマザーボードが自動的に実行する、メモリ設定の最適化処理のことです。
MSIに限らず、ほとんどのUEFI BIOSを搭載するマザーボードで実行される処理ですが、MSIはこのプロセスをユーザーに見える形で制御・再実行できるようにする独自機能を提供しています。
特に、XMP(eXtreme Memory Profile)などを有効にしている場合、高クロックメモリの動作を安定化させるために、このプロセスが重要となります。
このトレーニングは、メモリの動作タイミング(tCL、tRCDなど)や電圧設定、周波数などをハードウェアとBIOSが協調して自動調整する工程です。
メモリトレーニングの実行タイミングと体感
通常、メモリトレーニングはBIOS設定変更後の最初の起動時に自動的に行われます。このとき、画面が真っ暗なまま数秒~数十秒経過する場合がありますが、これは異常ではなく、マザーボードが適切な設定を試行錯誤している最中です。
特にDDR5メモリでは、電圧やタイミングが繊細であるため、トレーニングにかかる時間がDDR4よりも長くなる傾向があります。
現代の高速メモリ環境では、トレーニング処理の有無が起動成功率に直結するため、避けて通れないプロセスと言えます。
実際に行われる処理
実際にメモリトレーニングが何をしているか?という点で整理すると、以下4点になりますね。
データラインの遅延補正(Read/Write Leveling)
メモリチップとIMC間の距離や、DRAMチップ内のアクセスタイミングによって、各ビットの信号が届くタイミングにばらつきが出ます。
これをラインごとの信号伝送遅延(DQラインのSkew)を検出・補正するのがRead Leveling(読み出し)やWrite Leveling(書き込み)です。
BIOSはこの補正量を一つずつ試し、全ビットが安定して「1」または「0」として認識される遅延設定を探します。
タイミングパラメータの調整(タイミングマージン探索)
tCL、tRCD、tRP、tRASなど、メモリの各種タイミング設定について、動作可能な最小値を探します。
XMPやOC設定で限界に近い数値を設定しても、「自動的に微調整して通る値」に変更される場合があります。
MSIの「Memory Try It!」は、このタイミング探索にプリセットを活用して成功率を高める手法の一種です。
電圧設定の再評価
動作が不安定な場合、DRAM電圧(VDD)、VDDQ、VPP、VDDIOなどの電圧を自動で微調整することがあります。
DDR5では特に、PMIC(電源管理IC)がオンダイ化されており、電圧制御の複雑性が増しているため、この処理の重要度はさらに高まっています。
リンク構成とRank Detection
DIMMスロットごとに、シングルランク/デュアルランク/ダブルサイドなどの構成をBIOSが検出します。
メモリチップの物理配置や搭載容量によって信号のリフレッシュ周期やトレーニング方法も変わるため、BIOSはそれらを認識し、内部ルーティングを調整します。
便利なMSIの「メモリトレーニング」機能の特徴
MSIのBIOSでは、「Memory Training Retry」や「Memory Force Training」など、ユーザーがトレーニングの再実行を指示できる設定項目が存在します。
たとえばメモリの設定変更後にシステムがPOSTしない場合、手動で再トレーニングを実行することで、設定を再構築し、起動可能な状態に戻すことが可能です。
また、「Memory Try It!」という機能では、MSIが独自に検証した複数のメモリ設定プリセットを試すことができ、トレーニングと組み合わせて安定性を探る手助けになります。
一般的なマザーボードでは一度失敗するとCMOSクリアが必要な場面でも、MSI製品ではこのトレーニングリトライ機能により復旧の可能性が高まります。
MSIに限らずメモリトレーニングは現代の必須作業のひとつですが、大半は自動的に行われます。あまり意識する機会はないですが、メモリOCなどを実行するユーザーは気に留めておいたほうが良いでしょうね。